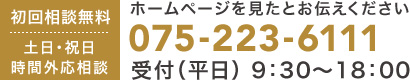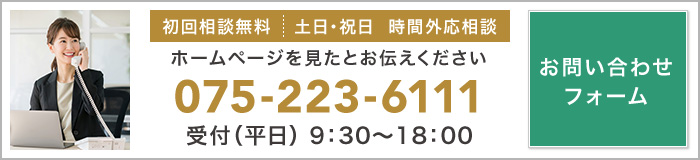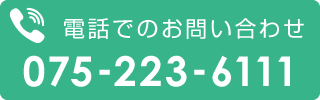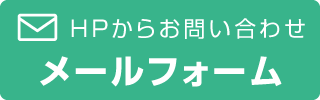このページの目次
1 養子縁組の要件について
養子とは親子関係を出生という血のつながりではなく、当事者の意思により生じさせる制度を言います。養子が成立するためには、形式的要件としては届出が必要ですが、実質的要件として縁組をする意思が必要となります(民法802条)。そして、養子縁組により親子関係が成立すると、養親が亡くなった場合、当然のことですが養子も相続人となります。
2 養子がいる場合の相続税の基礎控除額について
相続が発生した場合、遺産が多いと相続税を納めなければなりませんが、相続税の計算に当たり基礎控除が認められており、現行法では、3000万円に加えて600万円に相続人の数を乗じた合計金額の控除が認められております(相続税法15条1項)。例えば、相続人が3名の場合、基礎控除額は4800万円(=3000万円+600万円×3人)となります。
そうすると、遺産の多い人は、生前に自分の孫などを養子とすれば基礎控除額が増えることになりますので、節税のため養子縁組をして養子を増やそうとする人も出てくるかもしれません。しかしながら、この点については、相続税法上、被相続人に実子がいる場合は、相続税の計算上、相続人として数えられる養子は1人であり、被相続人に実子がいない場合には相続人として数えられる養子は2人となっております(相続税法15条2項)。つまり、相続税法上は、無制限に養子縁組をして養子を増やしても、基礎控除額として算入される養子を制限しております。
3 節税のための養子縁組は認められるのかどうかについて
では、そもそも節税のために養子縁組をした場合、果たして当事者間に縁組意思が認められるのでしょうか。
この点について、判例(最高裁平成29年1月31日・民集第71巻1号48頁)は「相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と認定しております。つまり、節税目的があったとしても、養親子関係を生じさせる意思が併存している場合は養子縁組を行う意思はあるとしました。当然のことながら、単に節税のためだけに養子縁組を仮装した場合は養子縁組の意思は否定されることになります。
もっとも、注意すべきことは、節税目的のための養子縁組につき縁組意思が否定されなかったとしても、実際に基礎控除額が増えるかどうかは相続税法の規定によることになります。つまり、相続税を不当に減少させる場合には、養子を基礎控除額の算定の相続人入れることができなくなりますので(相続税法63条)、専ら節税目的のために養子縁組を行うことは止めた方が良いと言えます。
相続のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。