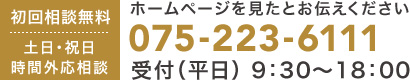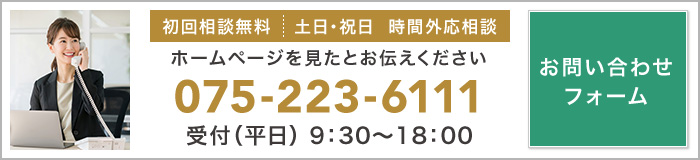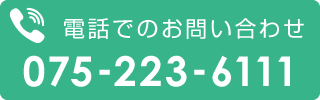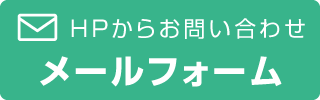令和2年4月1日に改正民法が施行され、賃貸借契約にも大きな影響を及ぼします。賃貸借契約の連帯保証人になる場合、連帯保証人が負担する最大限度額を取り決める必要があり、保証人が負担する最大限度額を極度額と言います。その取り決めがなければ保証契約は無効となります。その点は前回のコラムで記載しているとおりです。
このページの目次
1個人根保証契約の元本確定事由
改正民法では、賃貸借契約の終了をまたずに保証人の負担額が確定する事情を新たに規定しております(民法465条の4第1項)。法律用語では、保証人の負担額が確定することを「元本の確定事由」といいます。「元本の確定事由」は以下のとおりとなっております。
1. 保証人の財産に強制執行等がなされた場合
2. 保証人が破産した場合
3. 賃借人または保証人が死亡したとき
上記の元本確定事由が発生した場合、保証人は上記事情が発生した時点までの債務を支払う責任が生じます。例えば賃借人が死亡した場合、保証人は賃借人が死亡した時点までの賃料等の支払義務を負います。死亡時点以降に生じた賃料等の債務については責任を負う必要はありません。
2保証すべき対象債務について
注意すべきは保証人が保証すべき対象債務は賃料に限られるものではないということです。確かに保証すべき債務の多くが賃料であることは間違いないでしょうが、保証人は賃借人が賃貸人に対して負う可能性がある債務についてはすべて責任を負わなければなりません。例えば、原状回復費用や放置物の撤去費用などについても元本が確定するまでに発生していた場合、保証人は責任を負わなければなりません。
もっとも、賃貸借契約時に保証人の極度額を80万円としていた場合、元本確定時点の滞納家賃や原状回復費用などを合わせると80万円を超える場合でもあっても、保証人は80万円を超えて責任を負担する必要はありません。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。