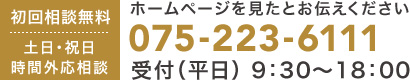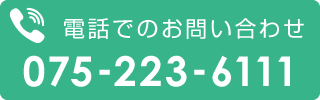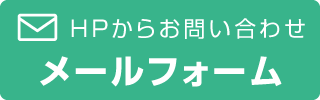Author Archive
フランチャイズ事案の解決事例
1 事案内容
依頼者は、不動産の退去立会の代行等をあっせんするフランチャイズ事業に加盟したのですが、フランチャイズ事業本部は、開業のための試験に合格しなかったことを理由として依頼者の開業を認めず、退去立会の代行のあっせんもしませんでした。訴訟提起前に依頼者の代理人弁護士からフランチャイズ事業本部に依頼者が支払った費用の返還を求めましたが、返還には応じてもらえなかったために、フランチャイズ事業本部を相手として損害賠償請求を求めて裁判所に提起しました。これに対してフランチャイズ事業本部からも違約金などの請求が反訴としてなされました。
2 事案の分析及び解決方法
訴訟での主な争点は、フランチャイズ事業本部の説明義務違反があるのか、依頼者の損害としての逸失利益が認れられるのか、依頼者にフランチャイズ事業に加盟するにあたって落ち度(過失)が認められるのかでした。他にも特定商取引法上の違反することについても争点としておりました。
判決では、開業可能性の有無の説明が適切になされなかったこと、適切な収益予測が提供されていなかったことなどが認定され、フランチャイズ事業本部の説明義務違反が認められました。
逸失利益についてはフランチャイズ事業に加盟しなければ他で就職して得られたであろう収入を求めていたのですが、この点については依頼者の請求は認められませんでした。
依頼者の落ち度(過失)ですが、通常、同種訴訟では、フランチャイズ事業といえども加盟者も独立した事業体であるとか、加盟者自身が加盟前にフランチャイズ事業をきちんと調査しなかったとか、加盟者が過去に会社経営や個人事業の経験があるなどを根拠として損害額の3割から7割程度の過失相殺がなされてしまいます。しかし、本件ではフランチャイズ事業本部が依頼者に対して開業可能性及び収益予測について不正確又は誤った情報を提供した著しい落ち度があるとして、過失相殺を一切認めませんでした。また、反訴においてフランチャイズ事業本部が求めていた違約金請求は認められませんでした。
フランチャイズ事業本部は高等裁判所へ控訴しましたが、控訴審においても第1審の内容がそのまま維持されることを前提で和解いたしました。
最終的に依頼者はフランチャイズ事業本部に支払った費用の全額の返還を受けることができました。
3 まとめ
本件は、当初フランチャイズ事業本部と交渉しようとしましたが、結局、話合いで解決できなかったため訴訟を提起して解決した事例となります。裁判所が依頼者の落ち度を一切認めずに依頼者が支払った費用の全額を損害と認めたことが他の同種訴訟では見られない点といえます。ただ、訴訟提起から控訴審での和解まで2年半程の時間がかかりました。やはり訴訟での解決は時間がかかることになり、長丁場の戦いとなります。なお、フランチャイズ事業については十分に検討されてから加盟をすることをお勧めいたします【フランチャイズ事業の加盟を検討している方へ | 京都市中京区で初回法律相談無料のアーツ綜合法律事務所】。
フランチャイズ事案でお困りの場合は、是非アーツ綜合法律事務所へご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
フランチャイズ訴訟雑感
これまでにフランチャイズ本部や加盟店から多くの相談を受けてきましたが、フランチャイズ事業もコンビニだけでなく実に様々な事業があります。中にはフランチャイズ事業として成り立つのか疑問に思うものもあります。
相談を受ける中でいくつかの訴訟を手掛けてきましたが、本部や加盟店のいずれの立場であっても訴訟で争うことは双方にとって「労多くして益少なし」という印象が拭えません。フランチャイズの場合、契約前に本部が提示した収益予測と加盟店が実際に開業した時の売上が大きく異なることから当初の説明と違うということで訴訟になるケースがほとんどです。
訴訟になると加盟店に本部の説明義務違反を立証する必要があるのですが、立証に成功して本部の説明義務違反が認められたとしても、損害を算定する段階で裁判所は加盟店も独立の事業者であるとかフランチャイズ事業を精査せずに安易に意思決定をしたなどの理由により過失相殺がなされてしまうので、認定される損害額がかなり減額されてしまいます。このように本部にとっては損害賠償責任が認められると事業の見直しを迫られるでしょうし、加盟店にとっては実際に被った損害額よりも低い額しか認められないことが多いといえます。
このような訴訟実態を考えると、フランチャイズ事業に加盟することを検討されている方は、検討している事業につき複数社からの説明を受けるとともに、自らも事業内容を納得するまで徹底的に検討し疑問があれば解消しておく必要があります。やはり安易に意思決定をしないことが重要といえます。一方、本部についても本部だけの利益追求の事業を構築するのではなく、本部・加盟店の双方が共存できる体制を構築すべきといえます。
以下の記事も参考にして見て下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
建物明渡し事案の解決事例
1 事案内容
依頼者はマンションのオーナーですが、ある部屋の借主が1年近くも賃料を滞納しており、その部屋には借主ではない人物も複数出入りしており、管理会社も借主と連絡が取れないことから、対応方法に困り相談に来られました。
2 事案の分析及び解決方法
依頼者から事実関係を確認すると、借主本人とはほとんど連絡が取れない状況であり、借主でない人物から依頼者や管理会社へ連絡がある状況であり、さらには借主ではない複数の人物が部屋に出入りしているということでした。
そのため、借主へ内容証明郵便を送付し、期限を設定した上、滞納賃料の支払いがなければ賃貸借契約を解除する内容証明郵便を送りましたが、借主は受け取らずに返送されてきました。そのため借主の部屋に投函されたとの記録を残すため、特定記録郵便で送達しました。当然のことながら、期限までに滞納賃料の振込みもなく、訴訟を提起することにしました。
しかし、今回のケースでは、借主でない人物の出入りが複数確認されていたため、実際に部屋に居住している人物が借主でない可能性も考えられたので、明渡訴訟を行う前に占有移転禁止の仮処分を行ないました。
占有移転禁止の仮処分を行っておくことで、明渡訴訟の途中で占有者が変わっても、新たな占有者に対しても強制執行により明け渡しが可能となります。
その後、明渡訴訟を提起した上で判決を取得しましたが、借主は任意に退去することはなく、最終的には強制執行を行いました。
3 まとめ
本件は借主が任意に退去しなかったので、建物明渡にかかる手続(仮処分-訴訟-強制執行)をすべて行いました(建物明渡請求の流れ)。借主が居直って、任意に明け渡しない場合、賃貸人が実力行使して借主を追い出すと、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう可能性がでてきてしまいます。一刻も早く退去してもらいたい賃貸人の気持ちもわかりますが、実力行使をしてしまうと元も子もありません(家賃滞納者に対して行ってはいけないこと)。
借主が家賃滞納して早急に退去してもらいたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。実際には、本件のように強制執行まで行うケースはあまりなく、それ以前の段階で任意に退去することがほとんどです。
そこで、借主が家賃を滞納しており明渡しを求めたい場合、是非アーツ綜合法律事務所へご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
民事信託の可能性について
1 信託とは
信託とは、日常生活ではあまりなじみのない言葉ですが、文字どおり財産を信じて託すことを言います。法律的には、ある人が信用できる親族や第三者に対して、不動産や金銭などの財産を託し、その親族や第三者がその財産を管理することを言います。財産を託す人を委託者といい、財産を託されて管理する人を受託者といいます。さらに、信託法では信託関係の中で利益を受ける受益者も登場してきます。
このように信託では、主に委託者、受託者、受益者の三者が登場することになります。
委託者が受益者を兼ねる信託を自益信託といい、委託者と受益者が異なる場合を他益信託といいます。信託行為は、委託者と受託者との契約により行われる場合、委託者が遺言により行う場合、委託者が信託宣言という方法で行う場合があります。
では、信託を利用することによって、利用者にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。信託は様々な場面で利用でき、とても便利な制度なのですが、いくつかの事例で説明いたします。
2 高齢者の財産保護のための利用事例
高齢になってくると判断能力が衰え、自らの財産を管理できなくなる場合がしばしばあります。この場合に成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することも考えられますが、同制度を利用すると、高齢者にとって不利益になることはできなくなりますので、相続対策などの財産運用や自宅を売却して老人ホームに入るなどの行為ができなくなる可能性があります。
そこで、民事信託を利用して、自分の子どもや他の信頼できる親族に財産管理を委託して、高齢者自らが受益者になっておけば、判断能力が衰えたとしても、受託者が財産を管理し必要な場合は処分することもでき、また委託者である高齢者は必要な生活費を受給できるので財産は守られることになります。
なお、民事信託を利用すると、受託者に所有権は移転しますが、受託者の個別財産とは別に管理することが義務付けられており、信託から生じる利益は受益者が得られるので、実際には不都合は生じることはありません。
3 夫婦間に子どもがいない場合の利用事例
夫の財産として居住不動産がある場合、夫が死亡後は妻及び妻の兄弟姉妹が相続することになるので、夫が妻に相続させるという遺言書を作成すること方法も考えられますが、その後、妻が亡くなれば妻の兄弟姉妹が相続することになります。夫がこの不動産について妻死亡後は夫の親族に残したいと考えている場合は信託を利用することが一つの解決策となります。
この場合、夫が委託者として、受託者を最終的に譲渡したい夫の親族にしておき、受益者を夫、夫死亡後は妻としておき、帰属権利者を夫の親族とする信託契約をすることになります。
このような信託を行うことで、夫死亡後は妻が従前どおり不動産に居住し続けることができ、妻死亡後は夫の親族が不動産を取得することができます。
上記利用事例はわかりやすくするために簡単な事例にしておりますが、民事信託はさまざまな場面において利用することができる制度になっております。
民事信託については、委託者及び受託者との間で信託契約書をきちんと作成しておく必要がありますので、弁護士のなどの専門家に相談することをお勧めいたします。
法律のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
離婚に伴う財産分与により生じる課税関係について
1 離婚の際に財産分与する者に税金がかかる場合があること
離婚する場合、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を分与しますが、通常は、夫から妻に財産を分与することになります。分与対象となる財産には、現預金、不動産、保険、自動車などの動産などが主なものになります。
通常、離婚する夫婦は、夫から妻もしくは妻から夫に財産の半分を渡せば、財産分与としては終了するので、税金については全く考えていないではないでしょうか。
しかしながら、離婚する場合、分与する側に譲渡所得税がかかることがあります。分与される側の間違いではないかと思われるのですが、分与する側に税金がかかる場合があるのです。特に分与財産の中に不動産があり、購入後に資産価値が上がっている場合は注意が必要となります。なお、分与される側については贈与税がかかるのではないかと思われるのですが、財産分与は贈与ではありませんので、離婚自体が贈与税や相続税を免れるために行われる場合などの例外的事情がない限り、原則として贈与税が課されることはありません。
分与する側に譲渡所得税がかかることにつき、判例がありますので以下紹介いたします。
2 判例について
事案は協議離婚に伴う財産分与として夫が妻に不動産全部を譲渡したところ、後日、夫が自分に億単位の譲渡所得税が課税されることを知って、妻への財産分与の錯誤無効を主張した事案となります。本件事案では、夫は自分に対して譲渡所得税が課税されることを知りませんでした。
事案は協議離婚に伴う財産分与として夫が妻に不動産全部を譲渡したところ、後日、夫が自分に億単位の譲渡所得税が課税されることを知って、妻への財産分与の錯誤無効を主張した事案となります。本件事案では、夫は自分に対して譲渡所得税が課税されることを知りませんでした。
当該事案は最高裁まで争われ、最高裁平成1年9月14日判決では、「離婚に伴う財産分与として夫婦の一方が、その特有財産である不動産を他方に譲渡した場合には、分与者に譲渡所得を生じたものとして課税されることになる。したがって、前示事実関係からすると、本件財産分与契約の際、少なくとも上告人において、右の点を誤解していたものというほかないが、上告人は、その際、財産分与を受ける被上告人に課税されることを心配してこれを気遣う発言をしたというのであり、記録によれば、被上告人も、自己に課税されるものと理解していたことが窺われる。そうとすれば、上告人において、右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、他に特段の事情のない限り、自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的には表示していたものといわざるを得ない。」と認定して、分与者である夫(上告人)の錯誤無効の主張を認めました。
3 譲渡所得税が生じることは多くない
離婚に伴う財産分与において、分与する側に税金がかかる場合があることを説明してきましたが、分与財産である不動産が人気の居住地区にあるなど、購入時点に比べて資産価値が上がっている場所でない限り、実際には譲渡所得税が生じることはほとんどありません。つまり、通常、不動産は購入時点の価値が最も高く、財産分与時点ではかなり下がっていることが多いため、財産分与時点では譲渡損(離婚時点の価値<購入時点の価値)になっていることから譲渡所得税が生じることはほとんどありません。
もっとも、不動産が文教地区にある場合や繁華街や駅が近いなど、購入以降も価値が上がる要素があれば、譲渡所得税が生じる可能性がありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。
法律相談のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
賃貸借契約における賃貸人の連帯保証人に対する請求が制限される場合について
1 賃貸借契約における連帯保証人の責任
マンションやビルなどの一室を借りる場合、賃貸人との間で不動産賃貸借契約を締結しますが、通常、賃借人は賃貸人から連帯保証人を求められます。連帯保証人は、賃借人とともに賃貸借契約から生じる賃借人の債務を負担することになります。例えば、賃借人が家賃を滞納していれば、滞納家賃を支払わなければならないですし、賃借人が物件を破損したりした場合は補修すべき責任を負わなければなりません。このように連帯保証人は責任が重くなる場合があるため、通常は親族になってもらうことが多いと思われます。
2 連帯保証人の負担義務の範囲が問題となった事例
賃借人が家賃を滞納してからかなりの期間が経過しているにもかかわらず、賃貸人が即座に明け渡しを求めることがなく、滞納家賃が多額になってから連帯保証人に請求してくることがあります。連帯保証人とすれば賃貸人から請求を受けて初めて滞納家賃が多額になっていることを知ることになります。このような場合、連帯保証人は賃貸人から請求された金額すべてを支払わなければならないのでしょうか。原則的には連帯保証人は全額支払う必要がありますが、一定の条件が認められれば、連帯保証人は全額を支払う必要はありません。
この点については区営住宅の賃貸借契約において、賃貸人が滞納家賃を連帯保証人に請求した事案において、連帯保証人への請求を制限した事例(東京高裁平成25年4月24日判決)があります。
この事案では、賃借人が賃料不払いを続けながら、賃貸建物を明け渡さない場合、賃貸人は、保証人の支払債務が保証契約上想定されるよりも著しく拡大することを防止するために、保証人との関係で解除権等を状況に応じて的確に行使すべき信義則上の義務を負うとされ、賃貸人が権利行使を著しく遅滞したときは、著しい遅滞状態となった時点以降の賃料ないし賃料相当損害金を保証人に請求することは権利濫用として許されないと判断されております。
実際には賃貸人がどの程度の期間、権利行使を放置すれば保証人への請求が権利濫用となるのかはケースバイケースなのですが、およその目安として2,3年と解されます。もっとも通常、期間のみならず、他の事情も考慮されて判断されます。
3 改正民法の規定について
このようなトラブルが多かったことから、2020年に改正された民法では、親族や知人などの個人が賃借人の保証人となる場合には、知らぬ間に滞納賃料が増大することを防ぐために、賃貸借契約において保証人が負担しなければならない最大限度の負担額(極度額)を定めておかなければならなくなりました(民法465条の2)。
改正された民法により、今後は前述したようなトラブルは減少すると解されますが、2020年4月1日以前に締結された賃貸借契約については、改正民法が適用されないので先ほどのトラブルが生じる可能性があります。
不動産のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
解雇処分をされた事案の解決事例②
1 事案内容
依頼者は勤務している会社から勤務態度不良等を理由として、いきなり解雇されてしまいました。依頼者は解雇予告手当ももらっておらず、また次の就業先も決まっていないため、途方にくれて当事務所へ相談に来られました。
2 事案の分析及び解決方法
依頼者から事実関係を確認すると、会社が主張する勤務態度不良等の内容が全く事実と異なっており、会社が主張する内容が仮に事実であったとしても解雇の要件を充たしているものとは到底解せないものでした(「不当解雇されそう・された方へ」)。
また、依頼者が勤務していた会社は外国法人であり、雇用契約上は会社の現地法が適用されるとの契約内容になっておりました。そして現地法では、労働者に対する解雇は自由に行うことが可能であり、解雇予告手当の支払も必要がないものでした。
しかし、依頼者は外国法人と雇用契約を結んでいるものの、日本国内で勤務していたため、法の適用に関する通則法12条(注)によれば、解雇権の行使については日本法が適用される事案でした。
そこで、会社に対していきなり訴訟や労働審判を申立てるのではなく、まずは交渉を試みました。当方は解雇に関する本件事案では日本法が適用されるため会社の解雇手続には理由がなく解雇は無効であることを主張しました。
しばらくは会社の担当者とやりとりを続けていましたが、最終的に会社は解雇処分を撤回し、依頼者の給料の4ヶ月分近くの解決金を支払い、依頼者は退職することで合意が成立しました。
(注) 法の適用に関する通則法12条
1 労働契約の成立及び効力について第7条又は第9条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労 働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行法規を適用すべき旨の意思表示を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立効力に関しその強行法規の定める事項については、その強行法規をも適用する。
3 まとめ
本件は訴訟や労働審判を申し立てることなく、交渉でまとめることができたため、依頼を受けてから2ヶ月程で解決に至りました。
勤務する会社から退職を求められたり、解雇されたりすると、従業員としてはどのように対処してよいのかわからず、自ら会社と交渉していくのは過度な負担となり困難と思われます。
そこで、退職勧奨や解雇処分を受けてお困りの場合は、是非アーツ綜合法律事務所へご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
賃貸人が通常の電気料金に様々な諸経費を加算して賃借人に請求することの可否
1 マンションやビルでの電気料金などの光熱費の請求
マンションやビルなどの一室を借りる場合、賃貸人との間で不動産賃貸借契約を締結しますが、一戸建てや家族用マンションであれば、通常、賃借人が電気、ガス、水道などの光熱費の料金は電力会社やガス会社と直接供給契約を結びますので、基本料金及び毎月の使用料は、自分たちが使用した分について請求されることになります。
これに対して、商業ビルでは様々な業態の個人や法人が賃借人となっていることもあり、賃貸人から毎月の賃料に電気料金や水道料金が加算された請求書にもとづいて支払っている場合がよくあります。賃借人の多くがこれらの光熱費についてほとんど疑問を持つことなく、請求されるままに支払っているのではないでしょうか。
2 賃借人が負担すべき電気料金が問題となった事例
賃貸人が未払の電気料金を請求し、賃借人が電気料金の払い過ぎを主張して裁判になった事例(東京地裁平成27年2月27日判決)があります。
事案は、ビルオーナーである賃貸人が、賃借人に対して電気料金を2年間滞納しているとして訴訟を提起したのですが、賃借人の方でも、賃貸人から電気料金を過大に請求されて払ってきたとして、過大に請求された金額の返還を求めて反訴を提起しました。
この事案では、賃貸人が、実際に賃借人が使用した電気料金に加えて、ビルの管理料や人件費、金利リスクなどを考慮して毎月の電気料金を請求しており、このような請求が認められるかが争点となりました。
結論としては、賃貸人と賃借人の間で、電気料金などの課金方法や計算方法などの取り決めがなされたこともなく、賃貸借契約書にも課金方法や計算方法の記載もなかったことから、賃貸人が通常の電気料金に管理料など様々な諸経費を加算して請求することは認められませんでした。一方で賃貸人に対し、賃借人が過大に支払った電気料金を返還するよう認めております。
3 賃貸借契約における電気料金や水道料金などの定め方
賃貸人としては、賃借人に対し、電気料金や水道料金などの光熱費を請求するにあたり、通常の使用量に諸経費を加算するのであれば、賃貸借契約時点で賃借人に対して、課金方法や計算方法を説明した上で賃貸借契約書にも明記しておく必要があるでしょう。
もっとも、諸経費を加算するとしても、あらゆる経費を電気料金などに上乗せすることは認められるとは解されず、関連機器の保守管理費など合理的な範囲に限定されることになります。上記裁判例でも電気料金に加算される費用としては関連機器の保守管理費のみが認められております。
賃借人としては、賃貸人からの電気料金や水道料金の請求額がどのように計算されているのか一度確認した方がいいでしょう。
不動産のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
経営者保証ガイドラインについて
1 経営者保証ガイドラインとは
経営者保証ガイドラインとは2013年12月に合理的な保証契約のあり方を示したものですが、中小企業の経営者の保証債務の整理のための準則についても策定している点に大きな特徴を持っております。法律ではないので法的拘束力はありませんが、主たる債務者、経営者そして金融機関などが遵守すべき内容とされております。
では、経営者保証ガイドラインを利用すると債務者にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
従来、中小企業の経営者は会社が金融機関から運転資金等を借り入れる場合、連帯保証を求められました。そして会社が破産手続を取る場合、連帯保証をした経営者も破産手続を取らざるを得ない場合がほとんどでした。そうすると経営者は自己名義の持ち家などの財産は破産手続の中で換金されてしまい、手放す必要がありました。しかし、経営者保証ガイドラインを利用すると、会社は破産手続を利用したとしても、経営者自らは破産する必要はなくなり、債権者へは経済的合理性の認められる範囲で一部弁済を行なえば、残額は免除を受けられます。また、信用情報機関への登録もなされません。
それに加えて破産手続を取った場合よりも多くの財産を残すことが可能となります。通常、破産手続の場合は原則99万円分の財産のみ手許に残せますが、経営者保証ガイドラインでは、それのみならず一定期間の生計費や華美でない自宅を残すことができます。
2 経営者保証ガイドラインの利用要件
経営保証ガイドラインは対象となる債権者全員の同意が必要となるとともに、以下の利用要件を充たす必要があります。
➀ 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
② 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること
③ 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、債権者に対し、財産状況を適時適切に開示していること
④ 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
⑤ 主たる債務者が破産手続等の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係 属し、もしくは既に終結していること。
⑥ 主たる債務や保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、債権者にとって経済的合理性があること
⑦ 保証人に免責不許可事由がないこと
なお、経営者保証ガイドラインは対象債権者については金融機関を想定していますが、これに限られるものではなく、リース会社などの保証債務ではない債権者も含めてもよいとされております。しかし、経営者が連帯保証人となっている金融機関以外の債権者を含めると、経営者保証ガイドラインでは債権者全員の同意が必要となるためガイドライン成立のハードルが高くなってしまいます。
上記利用要件を充足しているのであれば、経営者保証ガイドラインを利用した方がよいでしょう。
3 経営者保証ガイドラインの手続の流れ
経営者保証ガイドラインを利用した場合の手続の流れですが、対象債権者へ返済の一時停止の要請を行い、弁済計画案を策定し、債権者に対する説明・協議を行い、最終的には特定調停(手続機関としては中小企業再生支援協議会もあります。)を申立て、対象債権者の合意を得て調停を成立させます。
このように会社の代表者など経営者個人については、金融機関の保証債務があったとしても、今後は経営者保証ガイドラインを利用することによって、破産手続を取る必要がなくなります。
経営者の方で経営者保証ガイドラインの利用を考えられている場合、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。
解雇処分をされた事案の解決事例
1 事案内容
依頼者は勤務している会社から能力不足等を理由として、退職を求められておりました。そのため、当事務所へご相談に来られました。依頼者が当事務所で相談されてから、間もなく会社から解雇処分をされてしまい、当事務所へ正式に依頼することになりました。
2 事案の分析及び解決方法
依頼者から事実関係を確認すると、会社が主張する能力不足等の内容が事実と異なっており、会社が主張する内容が仮に事実であったとしても解雇の要件を充たしているものとは到底解せないものでした(不当解雇されそう・された方へ)。
そこで、会社側にも弁護士が就いていたこともあり、いきなり訴訟や労働審判を申立てるのではなく、まずは交渉を試みました。当方は解雇の理由がないことを述べ、解雇無効を主張しました。
しばらくは会社側の弁護士とやりとりを続けていましたが、最終的には会社側は解雇処分を撤回し、依頼者の給料の約半年分の解決金を支払うことにより、依頼者は退職することで合意が成立しました。
3 まとめ
本件は訴訟や労働審判を申し立てることなく、交渉でまとめることができたため、比較的短期間で解決に至りました。勤務する会社から退職を求められたり、解雇されたりすると、従業員としてはどのように対処してよいのかわからず、自ら会社と交渉していくのは過度な負担となり困難と思われます。
そこで、退職勧奨や解雇処分を受けてお困りの場合は、是非アーツ綜合法律事務所へご相談下さい。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
あなたの抱える問題の解決に全力を尽くします。まずはお気軽に当事務所の公式ホームページをぜひご覧ください。